2021-04-28
[コラム]日本史小話
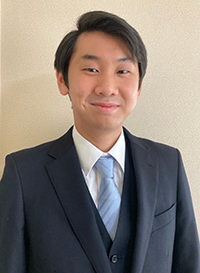
濱口先生(関西学院大学大学院文学研究科/日本史専攻)*執筆当時
日本の海賊とは -続-
日本史担当の濱口です。前回と同様に海賊のお話をさせていただきます。
海賊といわれると、略奪する者というイメージが湧きやすいかと思います。もちろん、海賊行為を行うことは、多々ありました。しかし、略奪するだけでありません。海賊はお金をもらい、明という中国の国家からやってくる商船を見回ったり護衛したりしていました。前回、西日本では海賊が警固衆と呼ばれていたという話をしましたね。警固衆の由来は、明の商船などを護衛したことからと考えられています。
また、海賊にお金を支払うことで航海の安全が確保できました。戦国時代最大の海賊と呼ばれた能島村上氏は紋幕*や写真にあるような旗をパスポートとして渡していました。また、パスポートの代わりに村上氏の家臣がその船に乗ることがありました。それを「上乗り」と言いました。さらに滋賀県の琵琶湖でも、「ひらひら」という旗のような物を渡して航海の安全を保障していました。瀬戸内海のみならず琵琶湖でもそのような文化があったのは、興味深いですよね。このように海賊は、略奪というマイナスの存在としてだけではなく、護衛というプラスの役割も担っていたのです。
日本の海賊の話はいかがでしたか。なかなか授業で聞くことがない題材だと思います。
次回は、戦国時代で一番有名な織田信長についてお話しします。
